10月30日、東京税理士会が主催する特別研修「A-Zセミナー」の第3回講義に参加してまいりました。
(参考:A-Zセミナーの概要についてはこちら)

第1回の家族法(相続)、第2回の法制実務(法律の読み方)に続き、
今回のテーマは、我々税理士にとって非常に大切な「租税法(税金の法律)」です
会場には約50名の受講生が集まる予定でしたが、
何度かセミナーを重ねるうちに、少しずつ欠席の方も見られるようになりました。
それでも、残った数人のグループで、熱心に議論を交わしました。

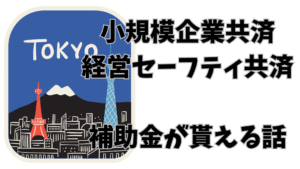
税金の基本ルール「租税法律主義」と株式評価の難しさ

今回の講師は、東京大学大学院教授の神山弘行先生。
テーマは「租税法」という、要するに「税金の基本ルール」のお話です。
「租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)」とは、「国民から税金を取るには、必ず法律(ルール)に基づいて行わなければならない」という、憲法で決められた大切な原則です。
しかし、この原則を守ろうとすると、時には複雑な問題が起こります。
なぜなら、税金には様々な種類があり、大きく分けて「フロー」と「ストック」という2つのものに課税されるからです。
- フロー課税
- お金や利益が「流れる(動く)」ことで発生する税金。
- 例えば、会社の利益にかかる法人税、個人の給料や事業の売上にかかる所得税などです。
- ストック課税
- 財産や資産が「ある時点において存在する量」に対してかかる税金。
- 例えば、土地や建物にかかる固定資産税
- 財産をもらったときにかかる相続税や贈与税などです。
このように、税金は私たちの経済活動の様々な側面に課せられます。
例えば、
- 社長が亡くなって、その会社の株式を子どもが相続する
- 社長が元気なうちに、子どもに会社の株式を贈与する
といった場合、もらった株式にいくら税金がかかるか計算するために、
その株式の「値段(価値)」を決めなければなりません。
でも、上場企業のように市場で値段がつく株式と違って、
個人が持っている中小企業の株式は、値段が分かりにくいんです。
また、税の世界では、「金銭の時間的価値」という考え方も重要になります。
例えば、今もらう100万円と、10年後にもらう100万円では、お金の価値が違う、という考え方です。
これらをどう税金に反映させるかも、租税法が向き合うべき課題です。
さらに、「税率を自分で選べるような場合は、その税金は実質的に『寄付』に該当すると判断された『ガンジー島事件』」という最高裁判例のように、
納税者が税金を自分で選べるような状況では、
その行為が租税法律主義の範囲内かどうか、
厳しくチェックされることもあります。
今回のセミナーでは、この「株式の価値」を巡って最高裁判所まで争われた、ある事件をグループワークで学びました。
第3回グループワーク ~株式の価値は誰から見るかで変わる?~

グループワークで出された【課題】は、
「最高裁判決令和2年3月24日」という、比較的最近の裁判例に関するものでした。
これは、相続や贈与で非上場株式をもらった時の「評価の仕方」についての問題です。
簡単に言うと、こんな状況でした。
- 大株主Bさんが株式をCさんに譲渡しました。
- Bさんが同年中に亡くなります。
- 相続人は、株式譲渡の所得の計算を75円で計算し、準確定申告をしました。
- この株式の評価額を巡って、国(税務署)とCさんの間で意見が食い違いました。
- 配当還元方式(将来もらえる配当金から評価する方法)だと、1株あたり75円
- 類似業種比準方式(似たような会社の株価と比べて評価する方法)だと、1株あたり2,505円
これだけ大きな差があると、当然、税金も大きく変わってきますよね。
特に問題になったのは、「株式の価値は、それを持つ人によって違うのではないか?」という点です。
- 亡くなった大株主Bさんにとっては、たくさんの株式を持っているので、会社の経営に大きな影響力があります。
- だから、株式の価値も高く評価されるべき、という考え方。(国の考え方)
- 一方、少数株主であるCさんにとっては、経営への影響力はほとんどありません。
- だから、購入するとしたら、もっと安くないと買わないだろう、という考え方。(相続人の考え方)
裁判所は、このような
「株式を手放した人(亡Bさん)にとっての価値」と、「株式を取得した人(Cさん)にとっての価値」が違う場面で、「どちらの立場から株式の価値を評価すべきなのか?」という難しい判断を迫られました。
私、岡崎がグループ発表を担当しました!
この複雑な課題について、私たちはグループで活発な議論を重ねました。法律の条文や過去の判例、そして現実の経済状況をどう考慮するか…。
最終的には、私がグループの意見をまとめて、皆さんの前で発表させていただきました。
手書きのマジックで、私たちのグループの考えを図示しながら、
少し緊張しつつも、なんとか発表を終えることができました。
まとめ

このグループワークを通して、私が改めて学んだことは、税金の法律は、書かれている言葉をただ読むだけでは不十分だということです。
特に、非上場株式の評価のように、専門的な知識と経験が必要な分野では、法律の「意図」までを深く読み解く力が求められます。
今回の事例のように、誰が、どんな状況で、株式を取得するかによって、その評価額やかかる税金が大きく変わる可能性があります。
そして、その評価額の解釈を巡って、国と納税者の間で深刻な争いが生じることも珍しくありません。
私たちは税金のプロとして、
- 複雑な法律の条文を正しく解釈する
- お客様にとって最も公平で適切な評価を行う
- 万が一の税務調査にも対応できるよう、根拠を明確にする
といった役割を担っています。
次回に向けて
次回のA-Zセミナー(第4回)は、11月17日(月)です。
テーマは「憲法」。講師は、専修大学法学部教授であり弁護士でもある増田英敏先生です。
税金のさらに上位にある「憲法」を学ぶことで、税務に対する理解を一層深めてまいります。
引き続き、学びを続けてまいります。










コメント