こんにちは、税理士の岡崎友彦です。
秋晴れの2025年10月10日、私が今年参加する東京税理士会の特別研修「A-Zセミナー」の第1回が開講され、早速参加してまいりました。
このセミナーがどのようなものかについては、以前こちらの記事でご紹介させていただきました。
あわせて読みたい
東京税理士会の次世代リーダー育成講座「A-Zセミナー」に参加
いつも当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。 今回の記事では、私(税理士岡崎友彦)が参加予定の東京税理士会が主催する「明日の税理士会...


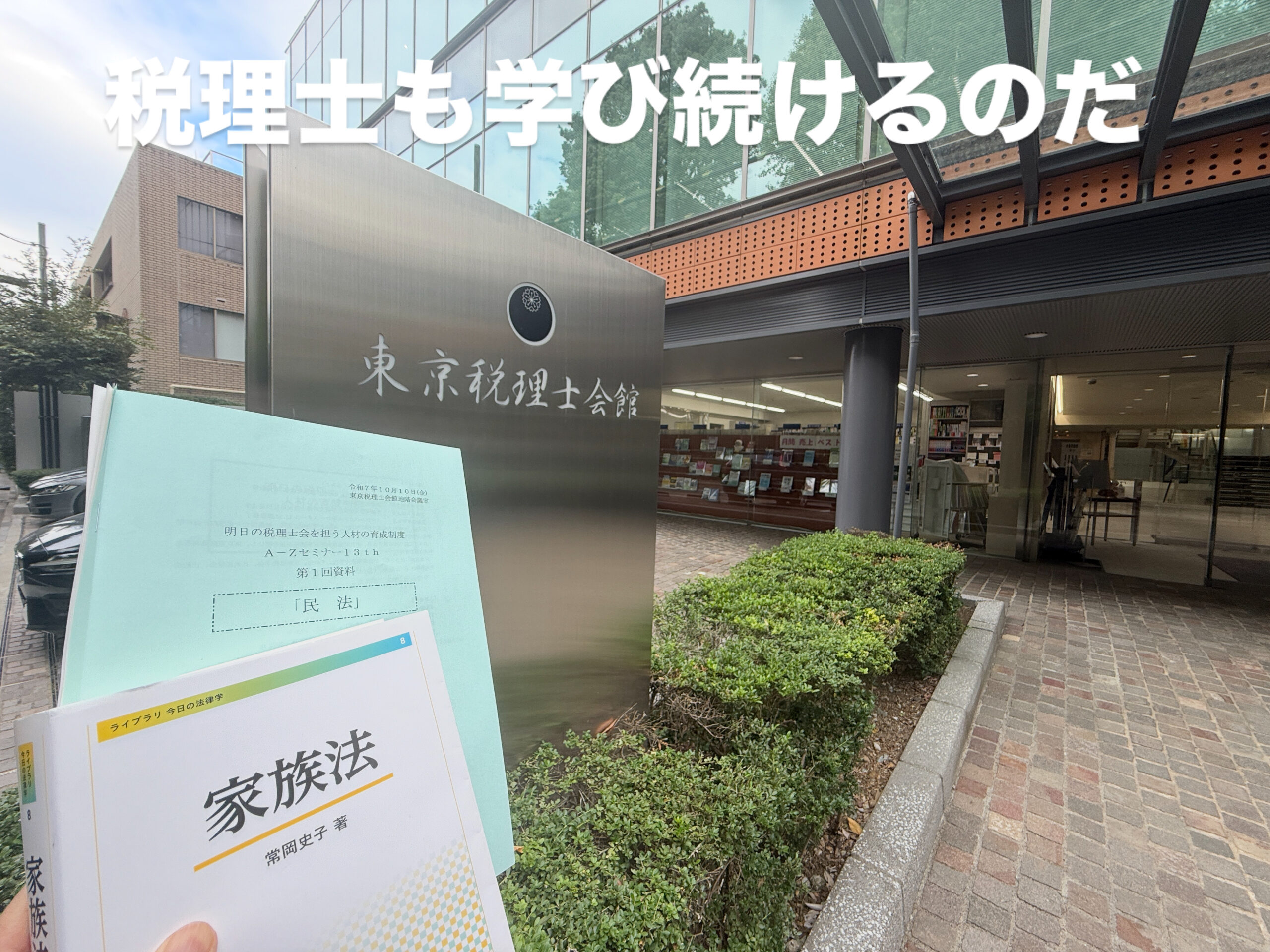









コメント