個人事業主として事業が軌道に乗ってくると、必ず向き合うことになるのが「税金」の問題です。
利益が増えるのは喜ばしいことですが、それに伴って納税額も大きくなります。
手元に少しでも多くのお金を残したい
事業の成長のために資金を有効活用したい
そうお考えの事業主様のために、今回は税理士として知っておいていただきたい、定番の節税方法10選を一つずつ分かりやすく解説します。
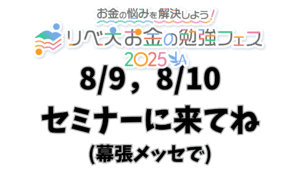
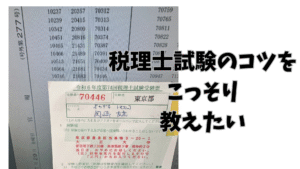
長期的な視点で取り組むべき節税策

まずは、一度手続きをすれば継続的な効果が見込める、計画的に取り組みたい節税策です。
1. 家族を「青色事業専従者」にして給与を支払う
ご家族が事業を手伝っている場合、その労働への対価を「青色事業専従者給与」として支払い、全額を経費にできる制度です。
- メリット
- 家族に支払った給与がまるごと経費になり、事業主の所得が減るため節税効果が高いです。
- デメリット
- 事業主は配偶者控除や扶養控除を使えなくなります。
- 給与額によっては家族自身の税金や社会保険料の負担が増えます。
- 個人事業税の計算では、青色専従者給与額がそのまま経費となりません。
- どんな人にオススメ?
- 配偶者やお子さんなど、実際に事業を手伝っているご家族がいる方
- 事業所得が多く、家族に所得を分散させることで世帯全体での節税をしたい方
- 要件は?
- 青色申告者であること
- 家族がその事業にもっぱら従事していること
- 生計を同一にする15歳以上の親族であること
- 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
- 給与額が仕事内容に見合った、社会通念上妥当な金額であること
2. もしもの備えと節税を両立「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」
取引先の倒産という不測の事態に備えつつ、節税もできる一石二鳥の制度です。
- 特徴
- 掛金は全額経費に算入できます。期末に最大240万円を一括で支払い、その全額を事業の経費にすることも可能です(掛金の上限は800万円)。
- メリット
- 取引先が倒産した際には、無担保・無保証人で掛金の10倍(上限8,000万円)まで融資を受けられます。事業のセーフティネットと節税を同時に実現できます。
- どんな人にオススメ?
- 特定の取引先への売上依存度が高いなど、連鎖倒産のリスクに備えたい方
- 利益の変動が大きく、利益が出た年に大きく経費を計上して将来に備えたい方
- 要件は?
- 事業を1年以上継続している中小企業者(個人事業主も含む)であること
- 業種ごとに定められた資本金や従業員数の要件を満たすこと
3. 経営者の退職金制度「小規模企業共済」
個人事業主には会社員のような退職金制度がありません。
この制度は、国が用意した「経営者のための退職金積立制度」です。
- 特徴
- 掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税を大きく節税できます。
- メリット
- 将来の退職金(事業廃止時の資金)を準備しながら、高い節税効果を得られます。
- iDeCoと違い、掛金の範囲内で低金利の貸付制度が利用できます。
- 事業の運転資金が必要になった際のセーフティネットとしても機能します。
- 個人事業主の方は、まずはこちらへの加入を最優先で検討するのがお勧めです。
- どんな人にオススメ?
- 将来の廃業や引退に備えて、ご自身の退職金を準備したい個人事業主や小規模企業の役員の方
- 所得控除による高い節税効果を得ながら、将来のための貯蓄をしたい方
- 要件は?
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主または会社の役員であること
4. 個人でできる節税・資産形成(NISA・iDeCo・ふるさと納税)
事業の節税とは少し異なりますが、事業主個人の手取りを増やす上で欠かせない制度です。
- NISA
- 投資で得た利益が非課税になる制度。直接的な節税とは異なりますが、効率的な資産形成に繋がります。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 掛金が全額所得控除の対象となり、高い節税効果があります。小規模企業共済と併用することで、さらに老後資金と節税効果を上乗せできます。
- ふるさと納税
- 応援したい自治体へ寄付をすることで、自己負担2,000円で返礼品を受け取れる制度。実質的に住民税などの前払いですが、返礼品の分だけお得になります。
- どんな人にオススメ?
- 所得税や住民税を納めており、将来のための資産形成も同時に進めたい全ての方
- 要件は?
- NISA: 日本国内に住む18歳以上の方
- iDeCo: 国民年金の被保険者であること(原則20歳以上65歳未満)
- ふるさと納税: 確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用すること(控除額は所得により変動)
決算期末に検討したい節税策
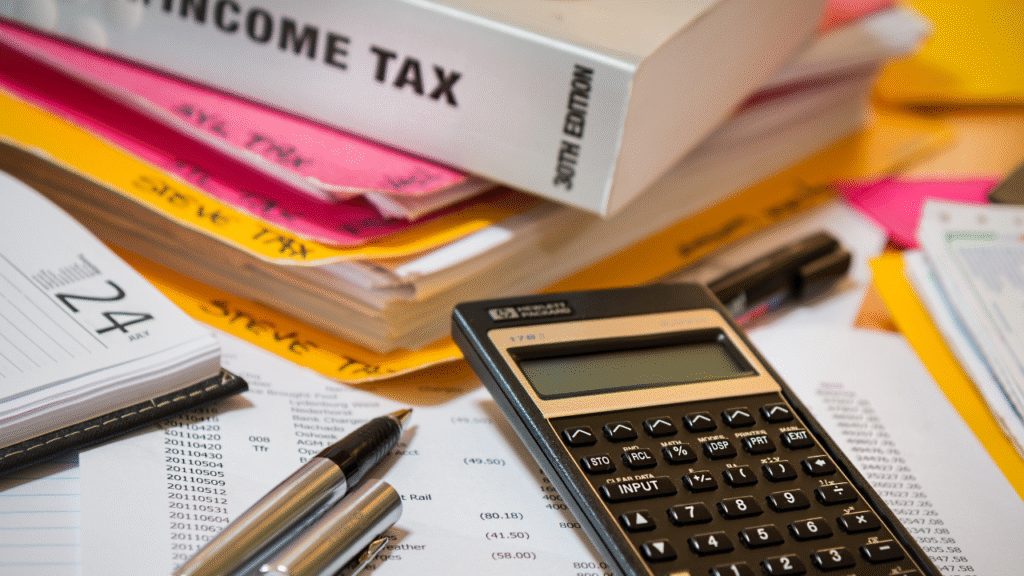
次に、利益の状況を見ながら期末に実施を検討できる、短期的な節税策です。
5. 消耗品などを期末に購入する
事業に必要な備品や消耗品を、利益が出た期の末に購入することで、その期の経費を増やす方法。
得意先への贈答用の商品券などを購入し、「接待交際費」や「広告宣伝費」として経費計上することもできます。
(※従業員へ配る場合は給与扱いとなるため注意)
- どんな人にオススメ?
- 決算月の利益が想定より多く出そうな方
- 近い将来に使うことが確定している消耗品や備品(PCなど)がある方
- 要件は?
- 事業に直接必要なものであること
- その年中に購入し、事業のために使用を開始していること(消耗品の場合)
- 金額が10万円未満の備品(青色申告者等の場合は30万円未満)であること
6. 不要な在庫を処分する
売れ残ってしまった在庫は、ただ持っているだけでは経費になりません。
- 方法
- 在庫をセール品として安売りして損失を確定させるか、廃棄して「廃棄損」として計上します。
- メリット
- 損失分を経費にできるだけでなく、在庫の管理コストを削減できるメリットもあります。
- どんな人にオススメ?
- 不良在庫や季節商品を抱えており、保管コストがかさんでいる方
- 期末の利益を圧縮したい小売業や卸売業の方
- 要件は?
- 実際に商品を廃棄した、または著しく低い価額で販売したという事実があること
- 廃棄した場合は、その事実を証明できる書類(廃棄証明書、写真など)を保管しておくこと
7. 不要な固定資産を処分する
使わなくなった古いパソコンや機械装置なども、ただ保管しているだけでは資産のままです。
- 方法
- 廃棄処分を行い、「固定資産除却損」として経費計上します。
- ポイント
- 買ってから日が浅いものでも、事業で使わなくなった場合は処分の検討対象となります。
- どんな人にオススメ?
- 使っていない古い機械やPCがあり、帳簿価額が残っている方
- 新しい設備への買い替えを検討している方
- 要件は?
- 実際に資産を廃棄・除却したという事実があること
- 廃棄の事実を証明できる書類(廃棄業者からの証明書、写真など)を保管しておくこと
8. 「前払費用」を計上する
翌期以降のサービス料などを、当期末までに支払うことで当期の経費として計上する方法です。
家賃や保険料、リース料など、1年以内の前払いが対象となるケースがあります。
- どんな人にオススメ?
- 翌年も継続して利用するサービス(事務所家賃、サーバー代、保険料など)がある方
- 期末の利益状況に応じて、納税額をコントロールしたい方
- 要件は?
- 年払いなどの契約に基づき、1年以内のサービスに対する対価であること
- その年中に支払いが完了していること
- 経理処理として、毎年継続して同じ方法を適用していること
継続適用が必要なため、効果は最初の1年のみになります。また、年払い契約に変更する必要があります。
1年分のキャッシュアウトを伴います。
9. 回収不能な売掛金を「貸倒損失」として処理する
取引先の倒産などで、どうしても回収できなくなった売掛金は、「貸倒損失」としてその期の経費に計上できます。諦める前に、経費にできないか検討しましょう。
- どんな人にオススメ?
- 取引先が倒産・夜逃げするなどして、売掛金が明らかに回収不能になった方
- 要件は?
- 法的な整理手続(破産など)により債権が切り捨てられた場合
- 債務者の資産状況から、全額が回収できないことが明らかである場合
- 取引停止後1年以上経過した場合など、一定の事実に基づいて回収不能と判断される場合
10. 貸倒れのリスクに備える「貸倒引当金」を計上する
売掛金や貸付金に対して、将来発生するかもしれない貸倒れに備え、一定額をあらかじめ経費として計上できる制度です。これにより、リスクに備えつつ当期の利益を圧縮できます。
- どんな人にオススメ?
- 売掛金や貸付金が多く、将来の貸倒れリスクに備えたい方
- 要件は?
- 期末に売掛金や貸付金などの債権を有していること
- 計上できる金額は、期末の債権残高に対して法定繰入率(5.5%など)を乗じるか、個別の事情を勘案して計算する
ただしご注意を!会社(事業)が潰れるたった一つの理由

ここまで様々な節税方法をご紹介しましたが、ここで一つ、税理士として最もお伝えしたい重要なことがあります。
それは、「キャッシュアウト(現金の支出)を伴う節税は、お客様の事業ステージを慎重に検討した上で実施すべき」ということです。
会社(事業)が潰れるたった一つの理由は何でしょうか???
 税理士 岡崎
税理士 岡崎…答えは、現金がなくなることです
期日までの支払いできなければ(現金がなければ)、事業の継続ができなくなります。
黒字倒産という言葉でも使われますね。
会計上では黒字でも売掛金の回収や、サイクルが回らないと給与や取引先への支払いができなくなってしまいます。
そのため、
例えば、節税のために無理に経費を使ったり、多額の共済掛金を支払ったりすると、確かに納税額は減るかもしれません。
しかし、それ以上に会社の現金が外に出て行ってしまい、結果的に手元資金が減ってしまうのでは本末転倒です。
節税の本来の目的は、無駄な税金を減らし、事業を成長させるための資金をより多く手元に残すこと。
目先の納税額を減らすことだけを考え、資金繰りを悪化させてしまっては元も子もありません。
お客様のステージに合わせた節税プランをご提案します


私たち岡崎友彦税理士事務所では、今回ご紹介したような節税方法をただ羅列してご提案するようなことはいたしません。
お客様の事業が今、「投資をしてでも成長を加速させるべきステージ」なのか、「内部留保を厚くして守りを固めるべきステージ」なのかをしっかりとヒアリングし、事業計画と資金繰りの状況を深く理解した上で、最適な節税プランを一緒に考えます。
「うちの会社に合った節税方法を知りたい」「無駄な税金は払いたくないが、お金はしっかり残したい」
そのようにお考えの事業主様は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
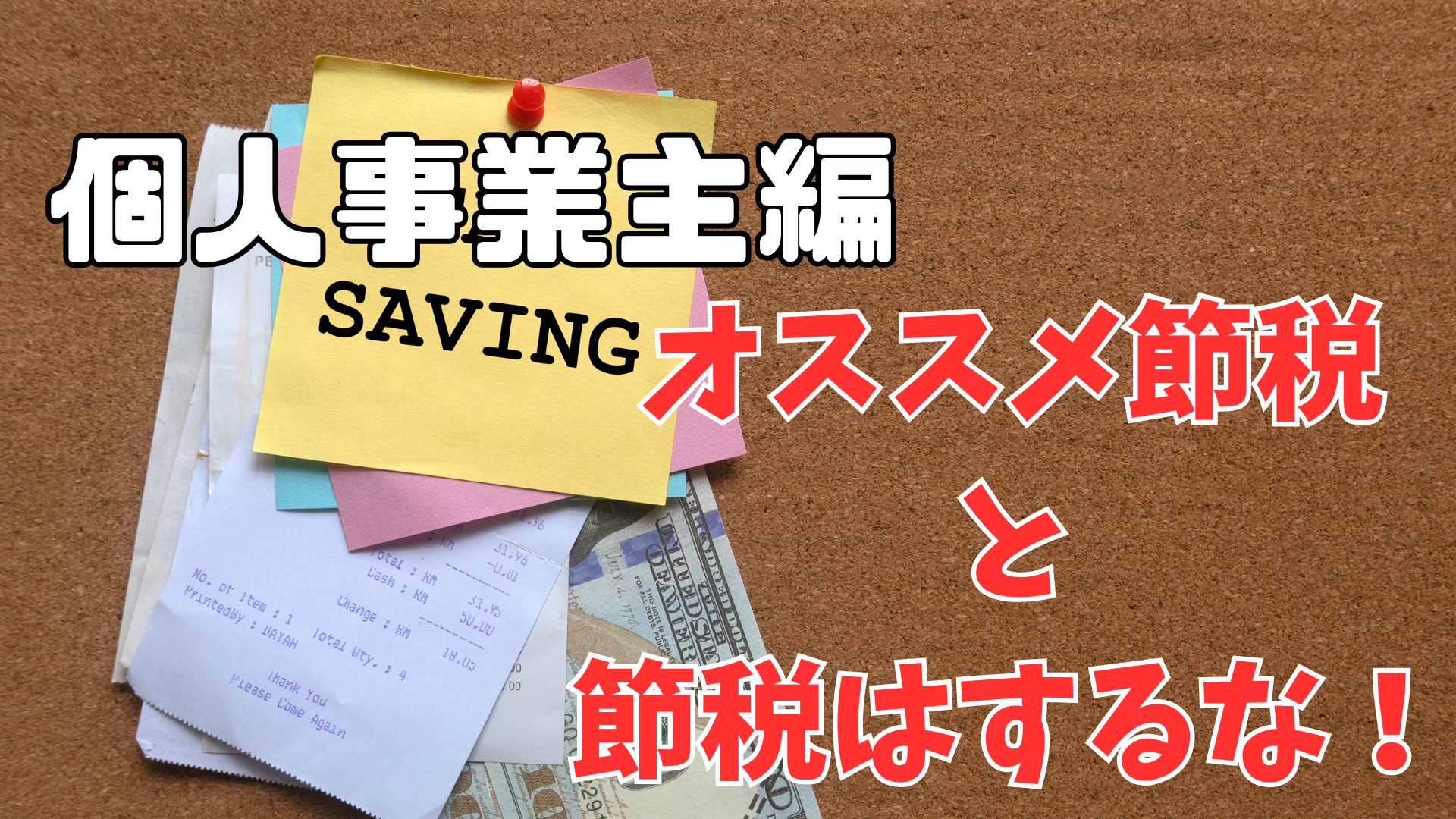












コメント