私は実務経験(会計事務所や税理士事務所などでの勤務経験)なしで税理士事務所を開業しています。
私のキャリアは以下でした。
- 理系大学の院卒
- 市役所勤務
税理士試験(5科目)に合格したとき、税理士登録をする際は、登録の仕方を選ばなければ登録申請ができません。


市役所職員から税理士合格後の実務経験について
まずは、実務経験が必要です。実務経験は税理士法第3条によると以下が該当します。
税理士法
(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
税理士法施行令
(会計に関する事務)
第一条の三 法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
税理士法基本通達
(税理士の資格としての実務経験)
3-1 法第3条第1項ただし書に規定する「租税に関する事務又は会計に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務又は会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)をいうものとし、この実務経験の期間は、税理士試験の合格の時又は試験全科目の免除の決定の時の前後を問わないものとする。
(特別な判断を要しない機械的事務)
3-2 令第1条の3に規定する「特別の判断を要しない機械的事務」とは、簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれるものとする。
(特別な判断を要しない機械的事務に該当しない事務)
3-3 次の各号に掲げるような事務は、簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とするものであり、令第1条の3に規定する「特別の判断を要しない機械的事務」には含まれないことに留意する。
(1) 簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務
(2) 仕訳帳等から各勘定への転記事務
(3) 元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
(4) 決算手続に関する事務
(5) 財務諸表の作成に関する事務
(6) 帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務
このうち私は、市役所で地方税に関する事務(徴収)を2年以上(4年)を経験していたため満たすことになりました。
市役所などで税金関係の事務を経験しているならば皆、該当するのではないでしょうか。
開業税理士・社員税理士・所属税理士の違いとは?
税理士は「開業税理士」「社員税理士」「所属税理士」の3種類です
開業税理士は、自分が税理士事務所を開き、税理士業務を行う人です。事務所のスタイルや使う会計ソフト、顧客獲得などすべて自分で決めていきます。税理士は個人事業主として活動し、従業員を雇うこともできます。
社員税理士は、2人以上の税理士が組織を作る「税理士法人」に所属して働く、その法人の役員相当の税理士のことです。
所属税理士とは、税理士事務所や税理士法人に雇用され、税理士業務を行う人です。上司や所長の指示に従い働くことになります。かつては「補助税理士」と呼ばれていました。
合格後のキャリア「会計事務所勤務or独立開業」それぞれのメリット
ここで、実務経験のない人が、「独立開業」をするか、「会計事務所」に入るかを考えます
会計事務所を経験するメリット
- 給与として安定した収入が得られる
- 一通りの実務経験が得られる
- 相談できる相手が上司や同僚にいる
実務経験がないのだから仕方がありません。まずは実務的な記帳や関与先(顧客)との関係づくりのスキルを身につけることができるし、安定な収入もあります。
実務の流れも、「教えてもらいながら」身につけることができます。
フルタイム勤務の就職の税理士は年齢や合格科目に一部考慮されるようですが400万円~みたいです。
独立開業はどうでしょうか。
独立開業のメリット
- 時間が自由になる
- 自分が決めた方針で仕事が進められる(ただし結果が出るとは限りません)
- 営業方法など経営者としての経験がつく
当初は顧客0で、収入はありません。実務もわかりません。
例えば、税理士が代行で行う場合のe-tax(WEB版)の使い方もわかりません。なお、自分の確定申告ではWEB版を使っていました。ましてやe-tax(ソフト版)の使い方もわかりません。
実務の流れは本で大まかな流れは読むことはできますが、大まかな流れがわかる程度です。
例えば、書類に印鑑は押すのか、細かい記帳のルールはどうすれば。契約書以外に個人情報保護の観点で考えることはあるか。など数え切れません。
それでも、得られるリターンは大きいと聞いています。
資産に余裕があったり、分からないことを進めていく人にオススメ。
第3の選択「業務委託でキャリアを積む」
最近は税理士業を「業務委託」として発注や受けることもできます。
この場合、業務量を調整することで、週の少ない日数で税理士として活動することもできるそうです。「税理士 業務委託 募集」などと検索すれば出てきます。
例えば、私が調べると
「法人税・顧問業務/準大手の税理士法人で業務委託パートナーを探しています。独立までのキャリア構築支援。独立希望者または既に独立している方を対象に、独立までのキャリア構築や独立後の支援を行う働き方です。」
が出てきました。
これならば、「自分の個人事務所の運営をしつつ」、「実務を経験することができる」
かも知れませんね。
みなさんの自身のキャリアアップの方針を進めるのか参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
<知識のアウトプット>

Xで税理士が弁護士から損害賠償請求を受けたという内容が話題になっています。
税理士が居住用家屋の譲渡特例と、住宅ローン減税の適用のアドバイスについて過失をしてしまい、その損害として弁護士から400万円の損害賠償請求を受けたという内容です。
またその税理士の方は苦しみから亡くなってしまっているようで、損害賠償請求を受けたのは、遺族の方のようです。
なお、googleで「居住用家屋の譲渡特例 住宅ローン減税 併用」と検索すると、
- 併用はできない
- 住宅ローン減税→居住用財産の譲渡特例 修正申告可
- 居住用財産の譲渡特例→住宅ローン減税 修正申告不可
- 年を跨ぐ場合は注意しなくてはならない
- 有利判定は事前に慎重に
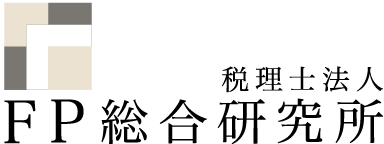
という内容です。
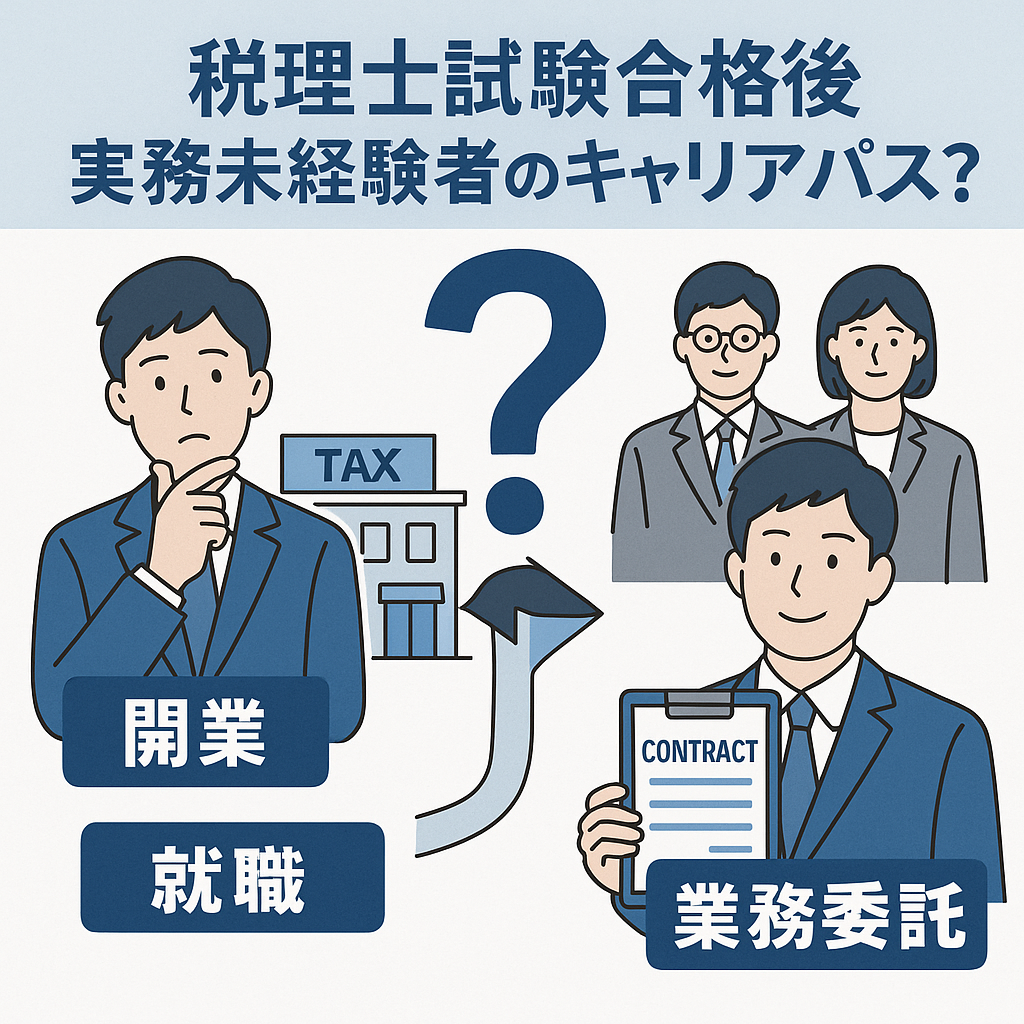









コメント