前回の記事では、個人事業主の方向けの定番の節税方法について解説しました。
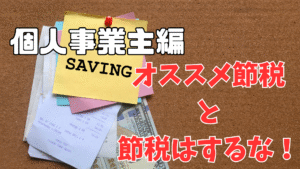
今回はその続編として、法人向けの節税対策に焦点を当ててご紹介します。
法人化の大きなメリットの一つは、個人事業主と比べて節税の選択肢が格段に広がることです。
ただし、その考え方には決定的な違いがあります。

個人事業主と法人の節税の考え方の違い

個人事業主の節税は、基本的に「事業の利益 = 事業主個人の所得」となるため、「個人の税金」をいかに抑えるかという一点に集約されます。
一方、法人の節税は、
- 法人が納める「法人税」
- 経営者個人が役員報酬に対して納める「所得税・住民税」
この2つの税金を会社と個人を一体として捉え、トータルの税負担が最も軽くなるポイントを探す、というより高度で戦略的な視点が求められます。
言葉だけでは分かりにくいので、具体的なケースで見ていきましょう。
【具体例】利益1,000万円、個人事業主と法人で手残りはどう違う?

仮に、事業の利益が1,000万円出たとします。
【個人事業主の場合】
利益1,000万円が、そのまま事業主個人の所得になります。
ここから各種控除を引いた金額に所得税・住民税などが課されますが、所得税は累進課税で税率が最大45%になるため、税負担は非常に重くなります。
- 税金(所得税・住民税・事業税・社会保険):約400万円
- 手元に残るお金:約600万円
- ※消費税や各種控除は考慮せず、あくまで大まかな計算です。
【法人の場合】
法人の利益1,000万円から、経営者個人に役員報酬500万円を支払ったとします。
- ①法人が払う税金 利益1,000万円 – 役員報酬500万円 = 法人の所得500万円 法人税等(実効税率 約22%と仮定):500万円 × 22% = 約110万円
- ②個人が払う税金 役員報酬500万円(給与収入)に対する所得税・住民税・社会保険 = 約100万円
- 合計の税負担と手元に残るお金
- 合計税額:約110万円 + 約100万円 = 約210万円
- 手元に残るお金(会社+個人):約790万円
表にすると
| 個人事業主 | 法人 | 差額 | |
| 税負担の合計 | 約400万円 | 約210万円 | -190万円 |
| 手元に残るお金 | 約600万円 | 約790万円 | +190万円 |
いかがでしょうか。
同じ利益でも、法人化して役員報酬という「利益の分配」を行うだけで、手元に残るお金が100万円以上も変わってくるのです。
このように、法人の節税は「法人」と「個人」の税金を一体で捉え、役員報酬というつまみを調整して、全体の税負担が最も軽くなるポイントを探す、戦略的なアプローチが求められます。
 税理士 岡﨑
税理士 岡﨑この点を念頭に置きながら、具体的な手法を見ていきましょう。
【1】長期的な視点で取り組むべき節税策編


1.役員報酬を設定する


法人節税の根幹をなすのが、この役員報酬の最適化です。
- メリット
- 法人の利益を個人の給与所得として移転できます。
- 法人税率と個人の所得税率のバランスが良いポイントに設定することで、法人・個人トータルの税負担を最小限に抑えられます。
- デメリット
- 一度決めた役員報酬は、原則として期中に変更できません。
- 変更すると経費として認められないリスクがあります。
- また、社会保険料の負担が発生します。
- どんな人にオススメ?
- すべての経営者。特に、利益が安定して見込めるようになった法人。
- 要件は?
- 事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定し、株主総会議事録を作成・保管すること。
- 毎月同額を支給すること(定期同額給与)。
2.役員賞与を設定する
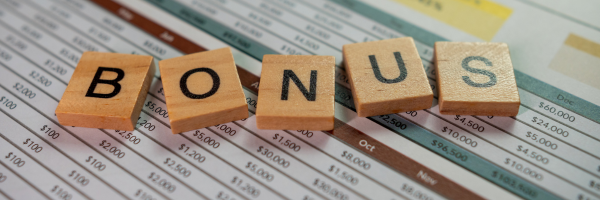
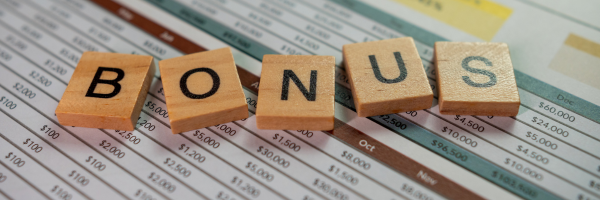
役員への賞与は原則として経費になりませんが、「事前確定届出給与」という手続きを踏むことで、経費として認めさせることができます。
- メリット
- 利益の出るタイミングに合わせて、役員へ賞与という形で利益を還元し、法人の利益を圧縮できます。
- また多額な賞与は、社会保険の上限額以上は、負担額も増えなくなります。
- デメリット
- 税務署へ事前に「いつ、誰に、いくら支払うか」を届け出る必要があり、その届出通りに支払わないと1円も経費になりません。手続きが非常に厳格です。
- どんな人にオススメ?
- 年間の利益がある程度正確に予測でき、特定の時期に大きな資金を役員個人に移したい法人。
- 要件は?
- 所定の期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出し、その内容と1円の狂いもなく支給すること。
3.家族を役員(非常勤役員)にする


生計を共にする家族を役員にし、役員報酬を支払うことで所得を分散できます。
個人事業主の青色事業専従者給与と考え方は似ていますが、法人の方がより柔軟な運用が可能です。
- メリット
- 世帯内での所得分散により、高い所得税率が適用されるのを防ぎ、世帯全体での手取り額を増やせます。
- デメリット
- 勤務実態に見合わない高額な報酬は、税務調査で否認されるリスクがあります。
- また、一定額以上の報酬を支払うと社会保険への加入義務が発生します。
- どんな人にオススメ?
- 経営相談や軽微な業務など、実際に会社の業務に関わっている家族がいる経営者。
- 要件は?
- 非常勤であっても、役員としての登記が必要。
- 勤務実態や貢献度に見合った常識の範囲内の報酬額であること。
4.出張旅費規程を整備する


「出張旅費規程」という社内ルールを整備することで、出張の際に役員や従業員へ食事代や諸雑費としての日当を支給できます。
- メリット
- 会社は日当を全額経費にでき、受け取った役員・従業員は非課税所得となります。
- 経費を増やしつつ、個人の手取りも増やせる一石二鳥の制度です。
- デメリット
- 規程の作成が必要です。
- また、日当の金額は社会通念上、妥当な範囲内(同業他社や会社の規模に照らして)である必要があります。
- 従業員が多くなると、キャッシュアウトが多くなってしまいます。
- どんな人にオススメ?
- 社長や従業員に出張の機会が多いすべての法人。
- 要件は?
- 全ての役員・従業員を対象とした「出張旅費規程」を整備し、株主総会議事録等で運用根拠を明確にしておくこと。
- 出張の事実を証明する報告書等を保管すること。
5.社宅制度を利用する


会社が物件を法人契約し、役員や従業員に社宅として貸し出す制度です。
- メリット
- 会社が支払う家賃と、役員等から受け取る一定額の家賃との差額を経費にできます。
- 個人が負担する家賃を会社経費に付け替える効果があり、個人の可処分所得が実質的に増加します。
- デメリット
- 物件の法人契約が必要です。
- また、役員等から一定額(社会通念上、家賃相場の50%程度が目安)の家賃を徴収しないと、給与として課税されるリスクがあります。
- どんな人にオススメ?
- 役員や従業員が賃貸住宅に住んでおり、福利厚生を手厚くしたい法人。
- 要件は?
- 会社名義で賃貸借契約を結ぶこと。
- 「社宅管理規程」を整備し、規程に基づいて役員等から適正な家賃を徴収すること。
【以下は節税商品】
将来への備えをしながら、会社の利益を圧縮できる制度です。
6.はぐくみ企業年金


「福祉はぐくみ企業年金基金」の愛称で、元本が保証される確定給付型の企業年金制度です。
従業員が自身の給与の一部を掛金として積み立て、会社が制度を導入・運営します 。
- メリット
- 従業員・会社双方の社会保険料負担が軽減されます。(掛金は給与と見なされないため)
- 従業員の所得税・住民税も軽減されます。
- 元本が保証されており、運用リスクがありません。
- 通常の退職時や休職時にも引き出すことができ、受け取りの自由度が非常に高いです。
- デメリット
- 会社側に月々の事務手数料(ランニングコスト)がかかります。
- 社会保険料の納付額が減るため、将来受け取る厚生年金額が減少する可能性があります。
- 大きな運用益は期待できず、資産を積極的に増やしたい方には不向きです。
- どんな人にオススメ?
- 投資の知識やリスクを気にせず、元本保証で安全に資産形成をしたい従業員が多い法人。
- 出産や育児などで短期の退職・休職が見込まれる従業員への福利厚生を手厚くしたい法人。
- 要件は?
- 厚生年金適用事業所であること。
- 経営者や役員も加入できますが、「一人社長」のみでの加入はできません。
7.企業型DC(企業型確定拠出年金)


会社が掛金を拠出し、従業員自身が投資商品を選んで運用する
確定拠出型の年金制度です。運用成績次第で、将来の受取額が変動します。
- メリット
- 運用次第では、将来の受取額を大幅に増やすことが可能です。
- 「一人社長」でも加入することができます。
- 掛金は社会保険料の算定基礎から外れ、会社・個人の負担を軽減できます。
- デメリット
- 従業員自身が運用を行うため、元本保証はなく、資産が減るリスクがあります。
- 積み立てた資産は、原則として60歳まで引き出すことができません。
- 従業員自身に一定の投資知識が求められます。
- どんな人にオススメ?
- ご自身の資産をご自身で積極的に運用し、大きなリターンを目指したいと考える経営者(特に一人社長)や従業員が多い法人。
- 長期的な資産形成を促し、定年まで勤める従業員への福利厚生を強化したい法人。
- 要件は?
- 厚生年金適用事業所であること。
- 制度の導入には、初期費用や運営管理手数料がかかります。
8.中小企業退職金共済(中退共)


国がサポートする中小企業向けの従業員の退職金制度。
会社が支払う掛金は全額経費として認められます。
役員は加入できませんが、福利厚生の充実が図れます。
- メリット
- 従業員のための退職金制度で、会社が支払う掛金は全額経費になります。
- 国の助成制度もあります。
- デメリット
- 役員は加入できません。従業員のための制度です。
- 一度加入すると、会社の都合で一方的に掛金を減額したり、支払いを止めたりすることはできません。
- どんな人にオススメ?
- 退職金制度を設けて、従業員の定着率を高めたい法人。
- 要件は?
- 業種ごとに定められた資本金や従業員数の要件を満たす中小企業であること。
9.経営セーフティ共済(倒産防止共済)


取引先の倒産に備える、国が運営する共済制度です。
掛金は全額経費になり、節税効果が非常に高いです。
もしもの時には、無担保・無保証人で借入れが可能です。
- メリット
- 掛金は全額経費になります。
- 期末に最大240万円を一括で前払いし、全額をその期の経費にすることも可能です。取引先の倒産時には無担保・無保証人で融資を受けられます。
- デメリット
- 掛金の上限は800万円です。解約時に戻ってくるお金は雑収入として課税されるため、出口戦略(退職金の支払いに充てるなど)を考えておく必要があります。
- どんな人にオススメ?
- 利益の変動が大きく、利益が出た年に大きく経費を計上したい法人。取引先の倒産リスクに備えたい法人。
- 要件は?
- 事業を1年以上継続している中小企業者であること。
【2】決算期末に検討したい節税策編
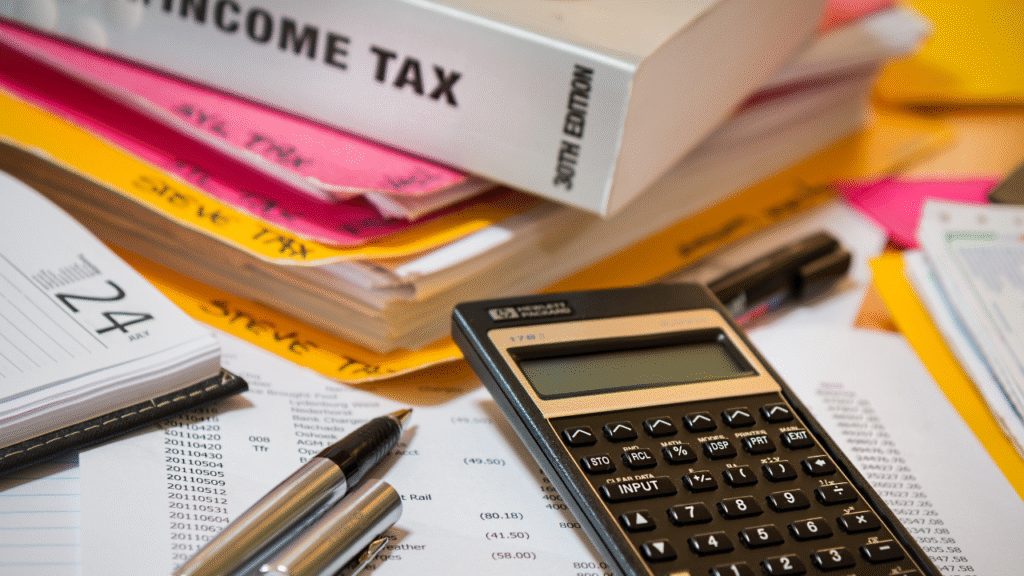
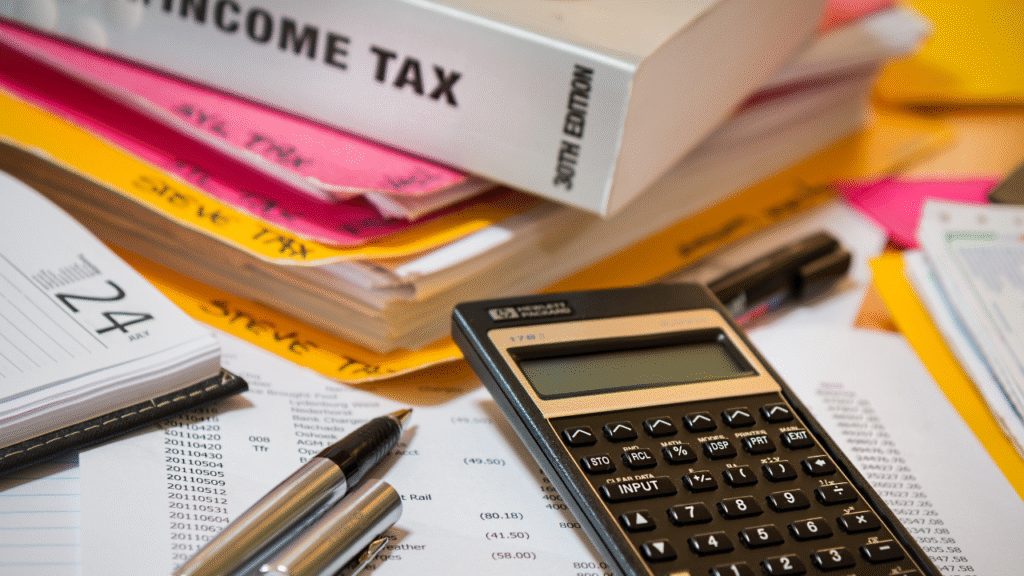
ここでは、決算月が近づき、年間の利益がある程度見えてきた段階で、最終的な利益調整として検討できる短期的な節税策をご紹介します。
1.決算賞与を支給する
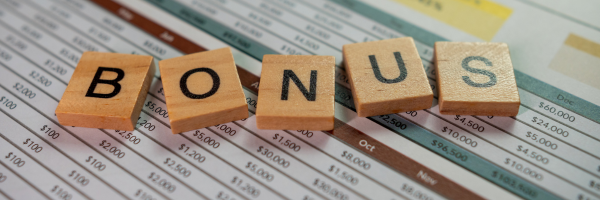
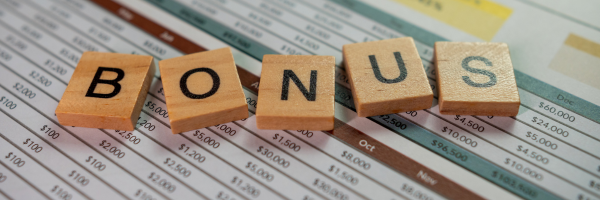
年間の利益を従業員へ還元するための賞与です。
- メリット
- 従業員のモチベーション向上に繋がり、会社の利益を圧縮して法人税を節税できます。
- デメリット
- まとまった現金支出(キャッシュアウト)が発生します。
- どんな人にオススメ?
- 想定以上の利益が出て、その貢献に報いる形で従業員へ利益を還元したい法人。
- 要件は?
- 原則として決算日までに支払う必要があります。
- ただし、「決算日までに各従業員へ支給額を通知」し、「決算日から1ヶ月以内に支払う」などの要件を満たせば、未払計上でもその期の経費として認められます。
2.期末に商品券などを買って配る


贈答用の商品券や消耗品などを期末に購入し、経費として計上します。
- メリット
- 比較的簡単に実施でき、少額の利益調整に有効です。
- デメリット
- 在庫として残るものは経費になりません。また、従業員へ渡す場合は「給与」として扱われ、源泉徴収が必要になる点に注意が必要です。
- どんな人にオススメ?
- 少額の利益調整が必要で、取引先への贈答品(接待交際費)や販売促進用の景品(広告宣伝費)として明確な使用目的がある法人。
- 要件は?
- 接待交際費や広告宣伝費など、事業上の明確な目的があること。領収書などの証拠書類を保管すること。
3.不要在庫の処分


売れ残った商品や使わなくなった原材料などを、セール販売や廃棄によって損失として計上します。
- メリット
- 帳簿上の資産を損失として経費化できます。また、保管スペースや管理コストの削減にも繋がります。
- デメリット
- 在庫の価値がゼロまたは低くなるため、将来得られたかもしれない売上を失うことになります。
- どんな人にオススメ?
- 不良在庫や季節商品を抱えており、保管コストがかさんでいる小売業や製造業の法人。
- 要件は?
- 実際に廃棄した、または著しく低い価額で販売したという事実が必要です。廃棄の場合は、廃棄業者からの証明書や写真などを保管しておくことが重要です。
4.不要な固定資産の処分


使わなくなった古い機械やパソコンなどを廃棄・売却し、帳簿価額との差額を損失として計上します。
- メリット
- 帳簿に残っている価値(簿価)を一括で経費にできます。買ってから日が浅いものでも、使わなくなった場合は対象となります。
- デメリット
- 資産そのものを失うことになります。また、廃棄にコストがかかる場合もあります。
- どんな人にオススメ?
- 使っていない古い設備が帳簿上に資産として残っている法人。
- 要件は?
- 実際に廃棄・売却したという事実が必要です。リース資産の場合は勝手に処分できないため、リース会社との契約を確認する必要があります。
5.前払い費用(短期前払費用)の計上


事務所家賃やサーバー代など、翌期以降に受けるサービスへの対価を、当期末までに1年分前払いして経費にする方法です。
- メリット
- 翌期の経費を当期に前倒しで計上できるため、突発的に出た利益を圧縮するのに有効です。
- デメリット
- あくまで費用の前倒しであり、翌期の経費がその分減るため、節税効果は一時的です。
- まとまった現金支出も伴います。
- どんな人にオススメ?
- 利益が大きく出た期に、納税を翌期以降に繰り延べたい法人。
- 要件は?
- 年払いの契約をサービス提供者と結び、実際に期末までに支払いを完了させること。
- 一度この処理を行ったら、翌期以降も継続して処理する必要があります。
ただしご注意を!会社(事業)が潰れるたった一つの理由


ここまで様々な節税方法をご紹介しましたが、ここで一つ、税理士として最もお伝えしたい重要なことがあります。
それは、「キャッシュアウト(現金の支出)を伴う節税は、お客様の事業ステージを慎重に検討した上で実施すべき」ということです。
会社(事業)が潰れるたった一つの理由は何でしょうか???



…答えは、現金がなくなることです
期日までの支払いできなければ(現金がなければ)、事業の継続ができなくなります。
黒字倒産という言葉でも使われますね。
会計上では黒字でも売掛金の回収や、サイクルが回らないと給与や取引先への支払いができなくなってしまいます。
そのため、
例えば、節税のために無理に経費を使ったり、多額の共済掛金を支払ったりすると、確かに納税額は減るかもしれません。
しかし、それ以上に会社の現金が外に出て行ってしまい、結果的に手元資金が減ってしまうのでは本末転倒です。
節税の本来の目的は、無駄な税金を減らし、事業を成長させるための資金をより多く手元に残すこと。
目先の納税額を減らすことだけを考え、資金繰りを悪化させてしまっては元も子もありません。
お客様のステージに合わせた節税プランをご提案します


私たち岡崎友彦税理士事務所では、今回ご紹介したような節税方法をただ羅列してご提案するようなことはいたしません。
お客様の事業が今、
- 「投資をしてでも成長を加速させるべきステージ」なのか、
- 「内部留保を厚くして守りを固めるべきステージ」なのか
をしっかりとヒアリングし、事業計画と資金繰りの状況を深く理解した上で、最適な節税プランを一緒に考えます。
「うちの会社に合った節税方法を知りたい」「無駄な税金は払いたくないが、お金はしっかり残したい」
そのようにお考えの事業主様は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
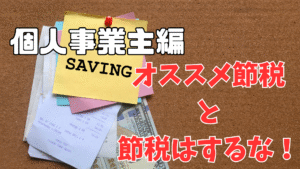
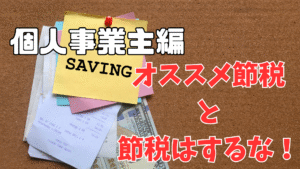
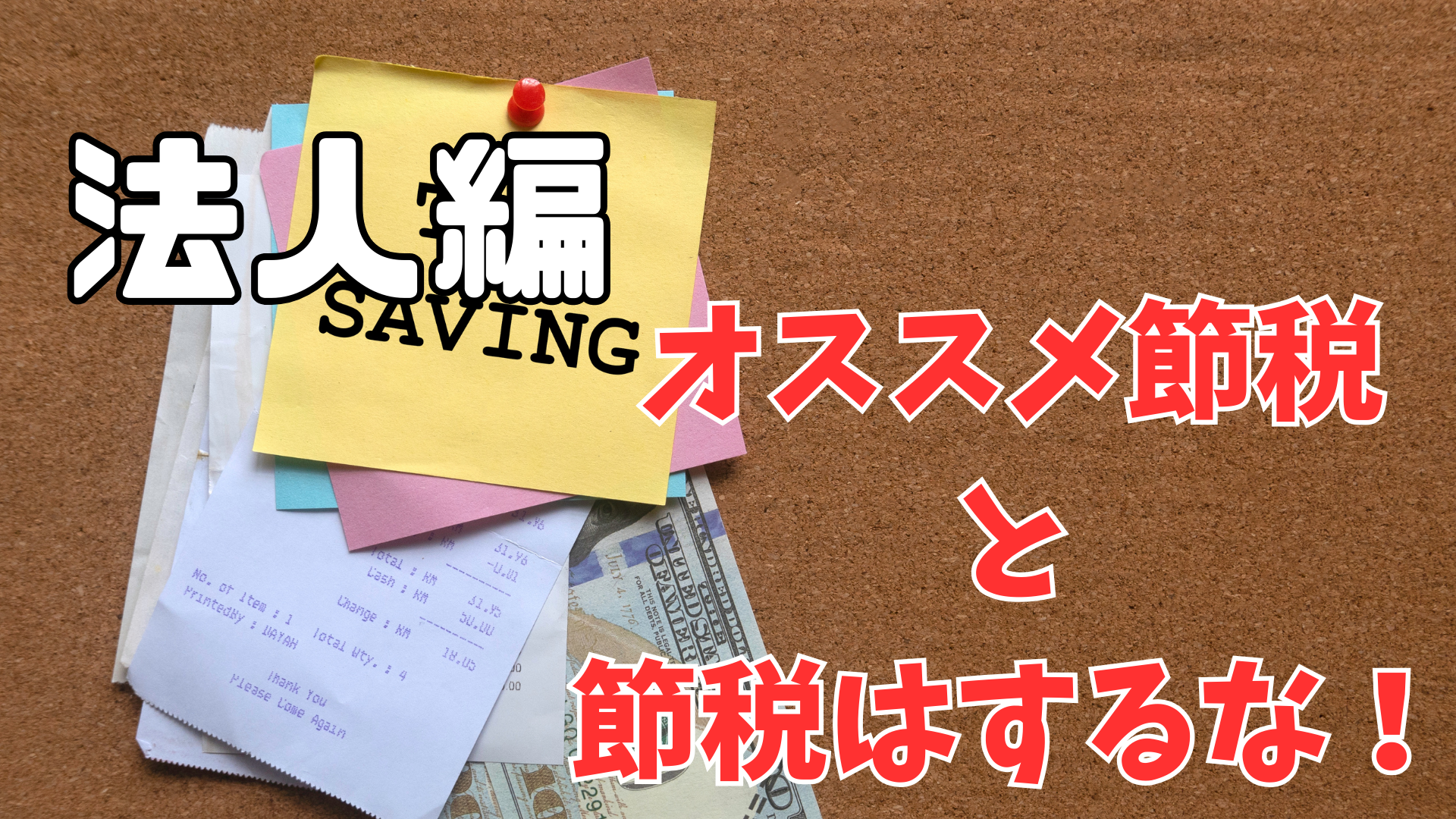



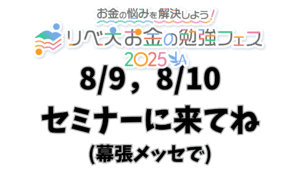
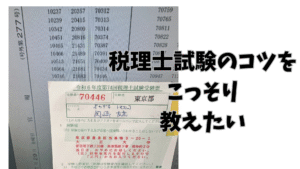
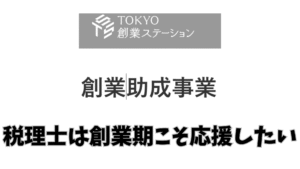

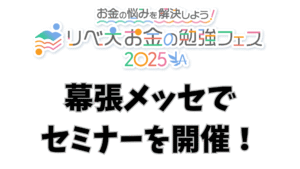
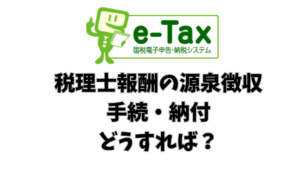
コメント