皆さん、こんにちは!
東京都荒川区を拠点に、全国へオンラインで税務サービスを提供する税理士の岡崎友彦です。
先日、少し珍しい場所での研修会に参加してきました。
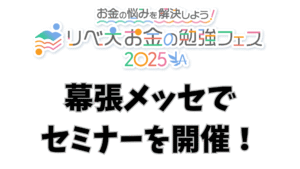
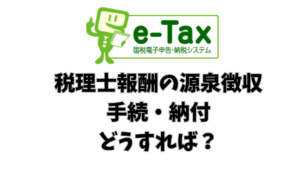
王子・板橋・川口・西川口・荒川の五支部合同の若手税理士懇親会

場所は、大井競馬場。王子・板橋・川口・西川口・荒川の五支部合同の若手税理士懇親会が開催されたのです。
平日の夜にもかかわらず、総勢50名近くの税理士が集まり、会場は熱気に包まれていました。普段なかなかお会いできない他の地域の先生方とも交流でき、私自身、この業界での横の繋がりが少しずつ広がっていることを実感できる、大変有意義な時間となりました。
夏の夜風が心地よい中、ナイター競馬の照明に照らされたコースを駆ける競走馬の迫力は圧巻の一言。
私も少しだけ馬券を買ってみましたが、結果は…見事にハズレ。普段の仕事では味わえない、純粋な悔しさを感じられたのも良い経験でした(笑)。

大井競馬場は都心からのアクセスも良く、場内には食事を楽しめる場所も豊富です。過ごしやすい季節の夜のお出かけに、皆さんも一度訪れてみてはいかがでしょうか。
さて、そんな楽しい懇親会の会場でしたが、そこは税理士の集まり。ただ競馬を楽しむだけではありません。会場の一角には「馬券裁判の研究ブース」が設けられ、非常に興味深い勉強会が行われていました。
今回は、その勉強会の内容を皆さんと共有したいと思います。
「競馬で儲かったら、税金ってどうなるの?」
この誰もが一度は抱く疑問について、プロの視点から深く掘り下げていきましょう。
競馬の利益は「一時所得」か「雑所得」か?

運命を分ける2つの所得区分
競馬で得た利益(払戻金)は、基本的には「一時所得」です。
しかし、判例によると、規模等により「雑所得」とできる場合もありあます。
どちらに分類されるかによって、納税額が天と地ほど変わる可能性があります。
簡単に違いを説明すると、以下のようになります。
- 一時所得: 一般的な競馬ファンの儲けが該当。営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得。
- 雑所得: 営利を目的として継続的に馬券を購入し、その利益が主な収入源となっているようなケース。
この区分がなぜ重要かというと、「ハズレ馬券が経費になるかどうか」という最大の違いがあるからです。
- 一時所得の場合: 経費として認められるのは、当たり馬券の購入費用のみです。そのレースで外れた他の馬券や、別のレースのハズレ馬券は一切経費になりません。
- 雑所得の場合: 一連の馬券購入が「事業」と見なされるため、年間のハズレ馬券代のほぼ全てが必要経費として認められます。
これがいかに大きな違いか、お分かりいただけるでしょうか。
税務上の運命を分けた、3つの重要裁判
この「一時所得か、雑所得か」という問題は、過去に何度も法廷で争われてきました。
勉強会では、その中でも特に有名な3つの裁判例が紹介されました。
競馬の税金を巡る代表的な裁判例
(TKC税情2023.4より)
- 最高裁 平成27年3月10日判決
- 納税者: 独自のソフトを開発し、市販の競馬雑誌のデータを基に、ほぼ全てのレースで網羅的に馬券を購入。
- 結果: 雑所得と認定。年間数億円規模の馬券を購入し、継続的に利益を上げていた実態が「営利を目的とする継続的行為」と認められました。
- 最高裁 平成29年12月15日判決
- 納税者: 長年の競馬経験に基づき、レースの格や距離などから独自の基準で馬券を購入。
- 結果: 一時所得と認定。購入に一貫した基準はあるものの、個々の馬券購入は独立したものであり、事業としての規模や継続性が認められませんでした。
- 最高裁 令和4年2月18日判決(高松事件)
- 納税者: ソフトウェアを用いてWIN5と通常馬券を自動購入。5年間で数千万円単位の購入を継続し、通算では利益が出ていました。
- 東京地裁: 継続性や規模から「雑所得」と認定。
- 東京高裁: 初年度の回収率が赤字(86.4%)だった点などを重視し、「収益性の継続が疑わしい」として「一時所得」と逆転判決。
- 最高裁: 上告を棄却し、高裁判決が確定。一時所得となりました。
高松事件が示す「雑所得」の厳しいハードル
特に3つ目の「高松事件」は、私たち専門家にとって非常に示唆に富むものでした。
この裁判から分かるのは、たとえソフトウェアを使い、長期間にわたって大規模な投資を続けていたとしても、「年間を通じて安定した収益を上げ続けられると客観的に認められる」レベルでなければ、雑所得とは認定されないということです。
通算で黒字でも、単年で赤字の年があれば、それは「事業」ではなく「偶然の産物」と見なされる可能性が高いのです。
つまり、一般の方が趣味で楽しむ競馬の利益が「雑所得」と認められることは、まずあり得ないと考えてよいでしょう。
具体的な税金計算はどうなる?
それでは、ほとんどの人が該当する「一時所得」として計算する場合、具体的にどうなるのでしょうか。
一時所得の計算方法
一時所得の金額は、以下の式で計算します。
(払戻金等の総額 - 当たり馬券の購入費用 - 特別控除額50万円) × 1/2
ポイントは2つです。
- 経費は当たり馬券代のみ: その当たりが出たレースで買った馬券の費用だけが経費です。
- 50万円の特別控除: 年間の一時所得の合計額から、最大50万円を差し引くことができます。
- 最後に1/2する: 計算された金額をさらに半分にしたものが、最終的な課税対象所得となります。
この金額を、給与所得など他の所得と合算して、最終的な所得税額を計算します。
税務署はあなたの儲けを知っている?
「少しくらい儲かっても、税務署にバレなきゃ大丈夫でしょ?」
そう考える方もいるかもしれません。しかし、その考えは非常に危険です。
JRAから税務署への情報提供
JRAの公式サイトには、以下のような記載があります。
勝馬投票券の払戻金は税法上、課税対象となるケースがあり、確定申告を要する場合がございます。
なお、「電話・インターネット投票」における約定に基づき、法的義務により競馬会が個人情報の提供を求められた場合(含む、「国税通則法 第74条の12第1項に基づく情報提供(注1)」) 、競馬会は電話・インターネット投票加入者(利用者)の個人に関する情報を保護措置を講じた上で提供するものとします。
注1:「国税通則法 第74条の12第1項に基づく情報提供」・・・1発売単位(100円)当たり1,000万円以上の払戻を受けた電話・インターネット投票会員(利用者)の情報提供
これは、「1回の払戻金が1000万円を超えるような高額当選者については、JRAから税務署へ情報提供が行われますよ」ということを意味します。
さらに注意が必要なのは、この基準に満たない場合でも、税務調査が行われた事例があるという点です。
「年間の」払戻金合計が1,000万円を超えた場合でも税務調査に入られた事例があるそうです。
税務署の調査能力を侮ってはいけません。元徴税吏員の経験から言っても、彼らはあらゆる合法的な手段を使って、課税対象となる所得を把握しようとします。
【具体例】1,000万円の払戻金、税金はいくら?
ここで、より具体的なイメージを持っていただくために、税額を計算してみましょう。
【前提】 給与収入300万円(諸々の所得控除を引いた後の課税所得は100万円と仮定)の方が、1万円の馬券を賭けて1,000万円の払い戻しを受けたとします。
一時所得の課税対象額を計算 (払戻金1,000万円 - 当たり馬券代1万円 - 特別控除50万円) × 1/2 = 474万5,000円
この474万5,000円が、給与の課税所得100万円に上乗せされます。
所得税と住民税を計算
- 所得税: 約67万円
- (合計課税所得574.5万円にかかる税額)-(給与所得100万円のみの場合の税額)
- 住民税: 約47.5万円
- (一時所得の課税対象額 474.5万円 × 税率10%)
【増加する納税額の合計】 所得税 約67万円 + 住民税 約47.5万円 = 合計 約114.5万円
このケースでは、払戻金1,000万円の約11.5%、おおよそ1割強を税金として納める計算になります。
もちろん、これはあくまで一例であり、元々の所得額によって税率は変わりますが、大きな払戻金には相応の納税義務が発生することを覚えておいてください。住民税もしっかりと含まれます。
まとめ:楽しい競馬ライフのために

今回の懇親会と勉強会を通じて、改めて「知ること」の重要性を感じました。
税金のルールを知っているかどうかで、手元に残るお金は大きく変わりますし、何より無用なトラブルを避けることができます。
最後に、競馬ファンの方々に覚えておいていただきたいことをまとめます。
- 競馬の利益は原則「一時所得」
- 他レースのハズレ馬券は経費にならない
- 年間の利益が50万円を超えたら確定申告を検討する
- 高額当選は税務署に把握されている可能性が高い
競馬はあくまで趣味の範囲で、健全に楽しむのが一番です。そして、もし幸運にも大きな利益を手にした際には、お気軽にご相談ください。
あなたの資産をしっかりと守るための、最善の方法をアドバイスさせていただきます。










コメント